今日は「会社を託す相手がいない…そのとき選べる道とは?」というテーマでお話しします。特に、60代以上の経営者の方で「自分が引退するとき、会社を任せられる人がいない…」と不安に感じている方はいませんか?実は、こうした後継者不在の悩みは決してあなただけではありません。東京商工リサーチによる調査では、中小企業の後継者不在率が実に60%以上にも上ることが報告されています。さらに、日本政策金融公庫の2023年の調査によれば、後継者が決まっている企業はわずか10.5%しかなく、なんと57.4%もの経営者が将来的に廃業を予定しているという衝撃的なデータもあります。後継者が見つからず、本当は続けられるはずの事業を泣く泣く畳んでしまうケースは年々増えているんです。
経営者の高齢化も深刻で、社長の平均年齢は過去最高の60歳超えとなっています。70代以上の社長も珍しくなく、「いつかは何とかなるだろう」と事業承継を先送りしていると、気付けば80歳近くまで現役…なんてことも。事業承継を先延ばしにした結果、「この先も事業は伸びるはずなのに、後継者がいないせいで廃業せざるを得ない」といった残念な例も少なくありません。実際、廃業予定の企業の約30%は自社に将来性があると感じながらも廃業を選択しているそうです。
後継者がいない経営者はどうすれば良いのでしょうか?大きく分けてこの動画では3つの選択肢をご紹介します。
それは、
- 従業員への承継
- 第三者への承継
- 計画的な廃業
 それぞれメリット・課題・具体的な対策がありますので、順番に見ていきましょう。
それぞれメリット・課題・具体的な対策がありますので、順番に見ていきましょう。
まずお伝えしたいのは「時間的余裕を持って計画し、実行すること」が何より重要だということです。一般に、ゼロから後継者を探すには5〜10年程度の準備期間が必要とも言われます。経営者が高齢になってから慌てて動いても、体調悪化などで計画が頓挫するリスクが高まります。ですから、「まだ大丈夫」と先延ばしにせずに、できるだけ早めに自社の将来について考え始めてください。このブログが、その第一歩を踏み出すヒントになれば幸いです。それでは、それぞれの選択肢について詳しく見ていきましょう。
1. 従業員承継(EBO/MEBO)

では、従業員承継のメリットから見てみましょう。
社風や技術が継承されやすい:長年会社に貢献してきた内部の人間が後を継ぐため、会社の文化やノウハウが途切れにくく、取引先や顧客にとっても安心感があります。現場をよく理解した人が新たな代表になることで、従業員にとっても引き継ぎのハードルが低いとされています。社内の信頼関係がそのまま次世代経営に引き継がれるのは大きな強みです。
従業員の士気向上:MEBOの形で従業員も株主になるケースでは、「自分たちの会社」という意識が芽生え、従業員のモチベーションが上がると言われます。社員が経営に参加することで、一丸となって会社を発展させようという前向きな空気が生まれやすくなります。
オーナーにとっての安心感:長年苦楽を共にした社員に託せることは、現オーナーにとって精神的な安心につながります。信頼できる“身内”に会社を譲れるため、「知らない第三者に渡すのは不安…」という悩みを和らげることができます。
一方、課題やハードルもあります。
資金調達の壁:最大の課題は買い取り資金を従業員側が用意できるかです。中小企業でも事業規模によっては億単位の資金が必要になることもあります。役員や従業員個人には十分な貯蓄がなく、多額の借入が必要となるケースが多いため、資金調達が難しいというデメリットがあります。現経営者から株式を買い取るにもお金がなければ始まりません。
信用力・保証の問題:従業員が株主となるEBOでは、会社に対する信用力(与信)が課題になります。銀行から融資を受ける際に、従業員個人では十分な実績や担保がなくスムーズに借りられない恐れがあります。また融資時の個人保証を誰が引き受けるのかという問題も避けて通れません。現オーナーが連帯保証していた借入金がある場合、それを新経営陣が引き継ぐのかどうか決める必要があります。さらに、複数の従業員が株主になる場合、後で社員が退職するとき株式をどう扱うかなどルール作りも求められます。
経営スキルへの不安:従業員や現場の管理職が必ずしも経営全般のスキルを持っているとは限りません。「技術はあるが経営は未経験」という場合、経営者教育や外部専門家のフォローが必要になるでしょう。また、社内の人間関係が変化することで、一時的に混乱が生じる可能性もあります。
こうした課題に対しては、いくつか具体的な対策・支援策があります。
金融機関からの承継ローンの活用:日本政策金融公庫や民間銀行には、事業承継向けの融資制度があります。例えば公庫の「事業承継・集約・活性化支援資金」を利用すれば、国民生活事業であれば最大7,200万円、中小企業事業であれば14億4,000万円までを設備資金・運転資金として別枠で融資を受けられ、据置期間も含め長期の返済計画を立てることが可能です。こうした制度を活用すれば、自己資金が不足していても承継の資金繰りを支えることができます。
信用保証協会の保証制度:信用保証協会では事業承継向けの特別保証制度を設けており、経営者保証(個人保証)を不要とする融資を受けられる場合があります。後継者が個人保証を提供しなくてもよい融資枠(最大2億8,000万円)を利用できる制度で、既存借入の借り換えによる保証免除にも対応しています。これにより、従業員承継後の個人保証リスクを減らすことが期待できます。
オーナーローン(売主ローン)やアーンアウトの活用:現オーナー自らが買い手(従業員側)に資金を貸し付けるオーナーローンや、一定期間の業績に応じて後払いで譲渡代金を受け取るアーンアウト方式も有効です。例えば、譲渡代金の一部を5年かけて分割で支払う契約にすれば、従業員側の初期負担を減らすことができます。業績連動のアーンアウト条項を入れておけば、会社の業績が計画どおり伸びた場合に追加でオーナーに支払う形にでき、買い手と売り手双方のリスクとメリットを調整できます。
従業員持株会・ファンドの活用:社内に従業員持株会を作り少しずつ株式を取得していく方法や、MBO/MEBOを支援するファンドや投資会社に協力を仰ぐ方法もあります。専門の事業承継ファンド(MBOファンドなど)から出資や融資を受け、従業員と共同で買収資金を調達した例もあります。プロの力を借りることで、自社だけでは難しい資金調達や承継手続きを円滑に進められる場合もあります。
このように従業員承継は、会社のDNAを残しつつ事業を引き継げる魅力的な方法です。一方で資金面・制度面の準備が必要不可欠なので、専門家や金融機関とも連携しながら計画的に進めることが成功のカギと言えます。
2.第三者承継(M&A、外部招聘)
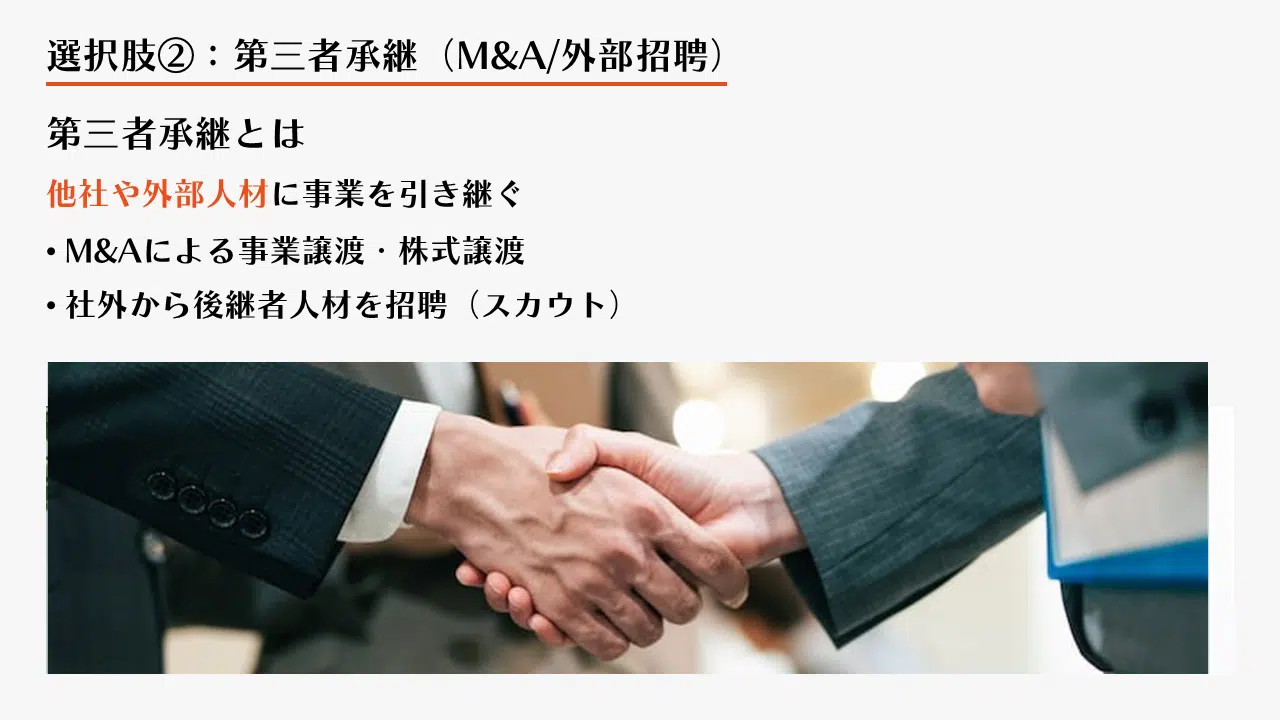
まずM&A型の第三者承継について、そのメリットを見てみましょう。
事業の継続・発展が期待できる:適切な買い手とマッチングできれば、会社は新たなオーナーのもとで事業を継続できます。むしろ体力のある企業に買われることで設備投資や人材投資が進み、売上や生産性が向上するケースもあります。第三者の力を借りて会社を存続・成長させられるのは大きなメリットです。
オーナーの利益確定と引退準備:会社を売却することでオーナーは株式の現金化が可能になり、創業からの利益を手にすることができます。これにより、老後の資金や個人保証の解除など経営者自身の人生設計を再構築することができます。また買い手との話し合いにより、一定期間は顧問や相談役として残りソフトランディングする取り決めも可能です。段階的に引退の準備を進められるのもメリットと言えます。
従業員の雇用維持:買い手企業との交渉次第で、「従業員の雇用継続」や「待遇維持」を契約条件に盛り込むこともできます。後継者不在で廃業すれば全社員の雇用が失われますが、M&Aで事業が引き継がれれば従業員の働く場が守られる可能性が高いです。「会社を畳むくらいなら、他社の傘下で存続させて社員の生活を守りたい」という経営者にとって、第三者承継は有力な選択肢になります。
取引先への影響軽減:主要な取引先にとっても、廃業よりは誰かに事業を引き継いでもらった方が安心です。例えば仕入先や顧客企業にとって、急に取引先を失うリスクが避けられます。地域や業界にとっても事業が存続する意義は大きく、M&Aによる事業承継は社会的にも価値があるのです。
こうしたメリットがある一方、第三者承継には独特の難しさもあります。
買い手探しの手間と難度:自社を買ってくれる相手を見つけるには時間と労力がかかります。特に中小企業では知名度も限られるため、自力で探すのは困難です。また業種や所在地、規模によっては希望する条件の第三者がなかなか見つからないことも。成約まで1~2年程度かかるケースが多く、時間的な余裕をもって取り組むことが重要です。
情報漏洩や従業員不安:M&Aを検討していることが社内外に漏れると、取引先や従業員が動揺しかねません。そのため極秘で進める必要があり、ストレスを感じる経営者もいます。買い手が見つかるまで通常業務を続けつつ、水面下で交渉を進めるのは負担が大きいと言えるでしょう。
企業文化の違い:第三者に会社を譲った場合、新オーナーの方針によっては社風や経営方針が大きく変わる可能性があります。従業員が新体制に馴染めなかったり、取引先との関係性が変化したりするリスクもあります。「せっかく譲っても会社がバラバラになっては意味がない」と心配する経営者も多いです。これは買い手選びの段階で文化的な相性を重視することである程度避けることができますが、完全にリスクをなくすことは難しいと言えます。
感情的ハードル:創業経営者ほど「赤の他人に会社を明け渡すなんて…」という心理的抵抗は強いものです。第三者承継では経営者自身が割り切れるかどうかという点も一つのハードルになります。
では、第三者承継を進める際の具体策や利用できる支援について触れます。
公的なマッチング支援:国や自治体は近年、中小企業の事業引継ぎを支援するためのマッチングサービスを充実させています。各都道府県に設置された「事業承継・引継ぎ支援センター」では、後継者を探す企業と事業を引き継ぎたい企業・個人とのマッチングを無料で行っています。また「後継者人材バンク」のように、外部から後継者候補となる人材を紹介する仕組みもあります。こうした公的機関に相談し、信頼できる第三者候補を探すこともよいと思います。
専門家(M&Aアドバイザー等)の活用:M&A仲介会社やFAに依頼すれば、自社の価値評価から候補先の探索、交渉支援までプロの力を借りることができます。仲介手数料はかかりますが、その費用の一部を補助してくれる制度もあります。国の「事業承継・M&A補助金」では、M&Aを行う際に専門家に支払う仲介手数料などに対し、上限600万円まで補助金が出ます(補助率2/3または1/2)。例えば本来900万円かかる手数料が600万円補助されれば、実質300万円の負担で専門サービスを利用できる計算です。公的補助を活用しつつ専門家と組めば、より良い条件でのM&A成立に近づけるでしょう。
外部後継者の招聘プラン:M&Aではなく、社外から経営者候補となる人材を迎え入れる方法も考えられます。例えば業界経験豊富なマネジメント人材を役員や後継社長として招き、数年かけて経営をバトンタッチする方法です。この場合、「所有と経営の分離」とう形になりますが、社長業を任せられる人材が確保できればオーナーは経営からは退いていけます。報酬面などコストはかかりますが、「会社は売りたくないが自分は引退したい」という場合に有効です。最近では大手企業OBや都市部の若手起業家などを地方の中小企業にマッチングさせる取り組みもあります。こうした人材マッチング支援も視野に入れてみてください。
第三者承継は、相手探しから契約成立まで時間と慎重さを要するプロセスです。しかし、「このまま自分の代で終わらせたくない。でも社内には後継者がいない」という場合には、社会全体としても推奨されている有力な選択肢です。国も中小M&Aを推進するため様々な支援策を講じています。ぜひ公的機関や専門家の力を借りながら、時間的余裕を持って検討してみてください。
3. 計画的な廃業
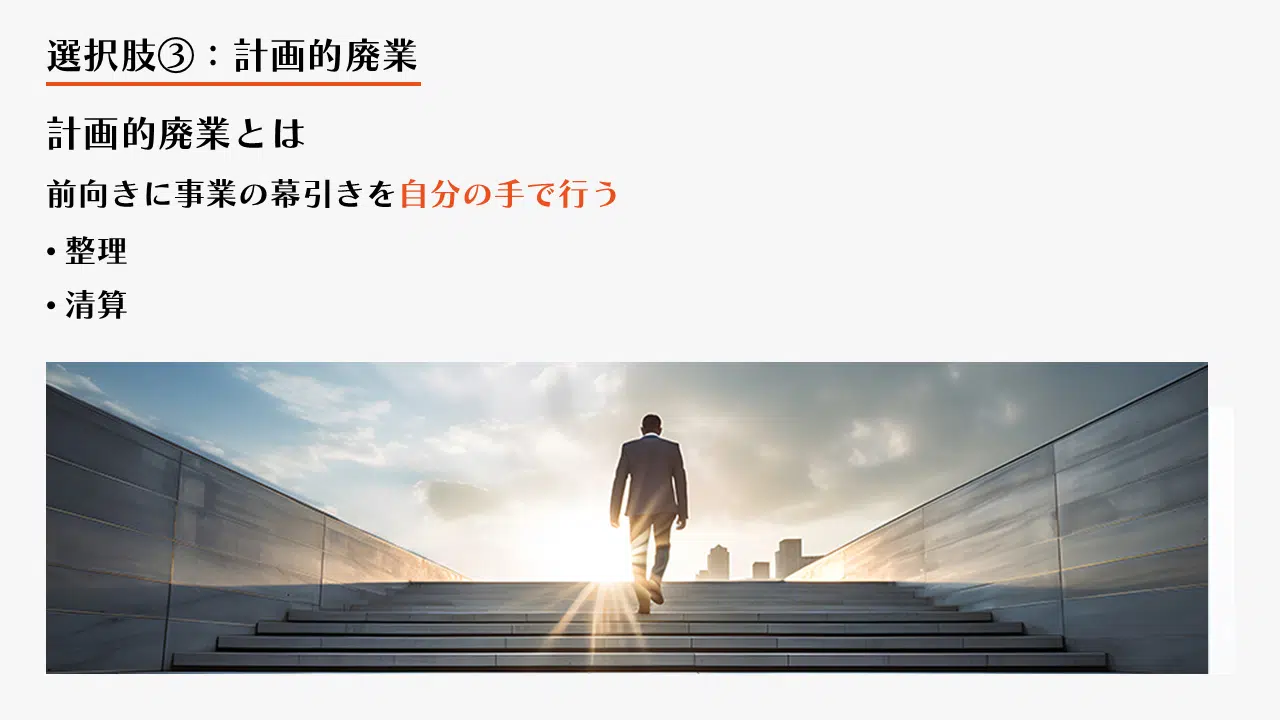
計画的廃業のメリット・ポジティブな面からお話ししましょう。
リスクの最小化:業績が黒字のうちに自主的に廃業すれば、債務超過に陥って倒産するような事態を避けられます。充分な資金がある状態で清算できれば、取引先への未払いなども発生せず、きれいな形で事業を終えることができます。経営が行き詰まってからの破綻より、余裕をもって撤退する方がトラブルも少なく安心です。
従業員や取引先への配慮:計画的に時間をかけて廃業準備をすれば、従業員には転職支援を行ったり退職金を上乗せしたりと、なるべく不利益が少ない形で送り出せます。取引先にも早めに事情を説明し、代替の供給先を紹介するなどフォローすることで信義を尽くせます。「店じまいの美学」ではありませんが、最後まで責任を持って関係者に対応することで、経営者としての有終の美を飾れるでしょう。
経営者自身の次のステップ:事業を整理することで、経営者は晴れて引退し、自分や家族の時間を取り戻せます。中には廃業後に新たな活動(趣味や地域貢献、またはスモールビジネスの再挑戦)に踏み出す方もいます。実際、国の事業承継・M&A補助金「廃業・再チャレンジ枠」では、廃業にかかる費用や廃業後の新事業準備を支援する制度もあります。廃業支援補助金を利用すれば、解散登記や在庫処分、従業員の再就職支援などに要した費用の2/3(上限150万円)まで補助を受けられます。つまり前向きに再スタートを切るためのサポートも用意されているのです。
とはいえ、廃業には当然デメリットや注意点もあります。
従業員の雇用喪失:事業自体が消滅しますので、従業員は職を失います。高齢の従業員が多い場合、再就職が難しいケースもあり得ます。この点は経営者にとって最も心苦しい部分でしょう。そのため、可能な限り早めに意思を伝えて準備期間を確保することが重要です。例えば「○年後に廃業予定」と前もって伝え、従業員が段階的に転職活動できるよう配慮する企業もあります。退職金や再就職支援金を手厚く用意することも検討すべきでしょう。
事業資産の処分:在庫商品や機械設備、不動産などを処分・売却する手間がかかります。場合によっては損失処理が発生しますし、専門業者への依頼費用も発生します。ただし在庫廃棄や解体の費用なども補助金の対象となり得ますので、上手に活用してください。
また、債務が残っている場合は金融機関との交渉や自己資金での清算も必要です。専門家(弁護士・会計士)のサポートを仰ぎ、法的に適切な手続きを踏みましょう。
心理的な負担:やはり「自分の代で会社を終わらせてしまう」という決断は辛いものです。特に創業者にとって廃業届に判を押すのは断腸の思いでしょう。この点、家族や周囲の理解・協力を得ながら進めることが大切です。経営者仲間や専門家に気持ちを相談しつつ、ご自身を責めすぎないことも忘れないでください。「会社を存続させることだけが社会貢献ではない。きちんと幕を引くことも責任ある経営だ」と自分に言い聞かせて、前を向いていただきたいと思います。
計画的廃業を成功させる(トラブルなく円滑に行う)ためのポイントも整理しておきます。
とにかく早めの意思決定と準備:廃業は重大な決断ゆえについ先延ばしにしたくなりますが、決めるなら一日でも早い方が良いです。時間に余裕があればそれだけ関係者への配慮も選択肢も増えますし、先延ばしにするほど状況は悪化して手遅れになることも多いです。廃業すると決めたら、遅くとも実行の半年〜1年前からは準備を始めましょう。法的手続き自体も、解散公告期間など最低2ヶ月以上は要します。在庫整理や設備の売却にも時間がかかるため、逆算してスケジュールを組むことが大切です。
専門家への相談:廃業手続きには法律・税務の専門知識が伴います。会社の状況によっては通常清算か特別清算か、あるいは破産手続きが必要かなど判断も異なります。信頼できる弁護士・税理士など専門家に早めに相談し、最適な進め方をアドバイスしてもらいましょう。専門家に依頼すれば、公告や各種届出、債権債務の清算など煩雑な手続きをサポートしてくれます。費用はかかりますが、最後にトラブルを残さないための必要経費と割り切って、プロの力を借りる方が安心です。
関係者への誠意ある対応:従業員、主要取引先、金融機関などには出来るだけ丁寧に事情を説明し、協力をお願いしましょう。突然の発表は避け、タイミングと言葉に配慮したコミュニケーションが重要です。たとえば社員へは十分な退職金や再就職支援策とセットで廃業を伝える、取引先へは紹介状を書いたり在庫品の安価提供を申し出る、金融機関へは事前に債務整理プランを相談する、等です。最後まで誠意を持って対応すれば、相手も理解を示してくれることが多いものです。
計画的廃業は決して「逃げ」ではありません。むしろ事業にけじめをつけ、ステークホルダーに責任を果たす立派な経営判断です。大切なのは、消極的な放置廃業にせず、主体的にプランニングすることです。必要な準備を整え、周囲と協調しながら進めれば、きっと円満に次のステップへ進めるはずです。
4. まとめ
最後に、今日お話しした内容のまとめ、皆さんへのメッセージをお伝えします。
「会社を託す人がいない…」という悩みへの選択肢として、(1)従業員への承継、(2)第三者への承継、(3)計画的な廃業の3つをご紹介しました。それぞれにメリットも課題もあり、どの道が最適かは会社の状況や経営者の想いによって異なります。
重要なのは、どの道を選ぶにせよ早めに動き出すことです。「まだ先の話」と思っていても、時間はあっという間に過ぎます。準備期間に余裕があればあるほど、選べる選択肢も増え、支援策も有効に活用できます。国や自治体も事業承継を支援するための制度を多数用意していますので、それらも上手に利用しましょう。
専門家や支援機関に相談することを躊躇する経営者は多いと思いますが、思い切って相談し、専門家とともにじっくり検討してみてはいかがでしょうか。
経営者人生の集大成として、「会社の未来をどうするか」という課題に向き合うのは大変勇気がいることです。でも、今日お伝えしたように道は一つではありません。そしてあなた一人で悩む必要もありません。同じ悩みを抱える仲間や専門の相談員が全国にいます。ぜひ一歩踏み出して、信頼できる人に相談してみてください。その一歩が、会社にとってもあなた自身にとっても、明るい次のステージへの第一歩になるはずです。
あなたの決断が、悔いのない、そして会社と従業員にとって最善のものとなるよう心から願っています。どの道を選んでも、これまで培ってきたものは決して無駄になりません。どうか自信を持って、次のアクションへ進んでください。
最後までご覧いただきありがとうございました。


